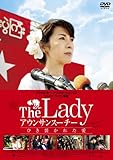『The Lady アウンサンスーチー ひき裂かれた愛』
劇中冒頭、父アウンサンが幼きスーチーさんの髪に、庭に咲いていたランの花を挿すところから始まります。
今年の4月に来日したスーチーさんがしている生花の髪飾りはシンボルマークとして多くの人の記憶に焼き付いていると思います。それはランだけでなくバラであったりジャスミンであったりするわけですが、特に思い入れの強いランの花は、自宅軟禁中であったために再会することなく死別した英国人の夫と、かつて誕生日に贈りあった品種であったといわれています。
この髪飾りは軍事政権に対する一種の抵抗であり国民に贈る希望を表すものであるようにも思えます。サッチャーさんを「鉄の女」と形容したように、スーチーさんを「鋼鉄の蘭」と言わしめるほどのその強い意志を蘭に見たということですが他にも、2010年に解除された15年にも及ぶ自宅軟禁からは「待ち続けた女」、基本的人権を取り戻すために闘っている姿から「女性版マンデラ」と呼ばれたりしています。
前回の記事で紹介したマンデラさんですね。
そうです、「ノーベル平和賞と民主化」つながりで今回の映画を観たわけです。
ちょっとここでその受賞者を振り返ってみます。
1990年 ミハイル・ゴルバチョフ(ソ連)
1993年 ネルソン・マンデラ と フレデリック・デクラーク(南ア)
2003年 シーリーン・エバーディー(イラン)
2010年 劉暁波(中国)
今はミャンマーと呼称されていますが1989年まではビルマでした。しかし軍事政権が国を名前を変えたということで欧米などでは政治的信条からミャンマーという改称を認めてはいません。なので今でもビルマと呼んでいます。
日本はミャンマーと深くつながっているのでその改称は認めていて劇中でも日本が民主化を援助しているシーンがあります。
歴史的にビルマを見てみると
1886年から英国による統治。1942年にアウンサン将軍が日本と共に英国を駆逐。翌年1943年にビルマ建国。で、いろいろあって、アウンサン将軍が暗殺され1962年にネ・ウィン将軍の軍事クーデターによりビルマは社会主義を標榜、といったという流れ。
映画はアウンサンが暗殺される直前まで時間を戻します。
ここからも分かるようにスーチーさんは活動家の血筋なんですね。今年のノーベル平和賞候補となっていた弱冠16歳のマララ・ユスフザイさんの一族も活動家。その信念たるや半端ない。頭に銃弾撃ち込まれてもまだ活動するんですから。こういった人たちは皆、DNAに果たすべき「義務」がしっかり刻み込まれているんでしょうね。いや、そんな特定の人だけじゃなく僕たち一人一人にそれぞれの義務が刻まれているはず。。なんだけどこういう活動家を目の当たりにすると自分のこのちっぽけさ!ってなるよね。まぁでもちっぽけな人間万歳とも思ってますけどね。
さて、スーチーさんは前回のマンデラさんとは少し違った攻め方をしています。スーチーさんは完全なる非暴力、誰の命も失なってはいけないという平和的方法、ハンガーストライキによる交渉戦、そうつまりガンジー精神がそこにある。
情け容赦なく国民を殺しまくる政権に対して彼女は待つしかなかった。最悪の心構えをして、最高を望み続けながら。
ここでちょっと時間を映画鑑賞前に戻します。
この映画の監督を知ってびっくりしたんですけど、なんとあのリュック・ベッソン。
10年くらい前に、あと何本か撮ったら引退するっていってたのに・・と思って調べてみると3年前に引退宣言撤回してましたね。知らなかった。(監督作ではなくて製作や脚本に関わっている娯楽作品はこれまでに沢山あり)
これはそんな監督の作品なので観客の感情に訴えかける物語にしなければならない。これもまた監督の義務であるんだろうと思います。スーチーさんを多くの人に観てもらう、そして知ってもらうためには、こういう愛の物語に仕立てる必要があったと。現実はほんとに厳しく重い。でもここでは鋼鉄の意志を持った活動家としてのスーチーさんではなく、今まで知ることがなかった母親としての、女としてのスーチーさんが描かれている。家族の絆を描くことに重きを置いています。とりわけ夫婦愛にいたっては夫が命ある限りに果たした役割を大きく取り上げている。
妻の身を護るためには国際的に高い評価を得ること、それがノーベル平和賞を受賞することだと考えた彼は委員会を説得することを、そして受賞するまでの長い長い時の中、妻へのその変わらぬ愛を、遠く離れて会えない状況に置かれながらも幸福を運び届けることを義務としていた。
蘭の花言葉のように。
義に務めるということ。それが自由ということなのかな。映画を観ていて、好き勝手やってる軍事政権側よりも民主化運動をしている国民民主連盟の方が自由に見えて仕方なかった。
それでは最後にアウンサンスーチー女史の言葉を
「私たちの自由のために、あなたの自由を行使してください。」